


このワインを探す
REVIEWS
| ワイン | Joseph Drouhin Côte de Beaune Blanc(2018) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | |||||||||||||||||||||
| 味わい |
| ||||||||||||||||||||
| 香り | |||||||||||||||||||||
| 詳細 |
|
COMMENTS
ドルーアンのコート・ド・ボーヌ・ブラン、良いですね!(^q^) クロ・デ・ムーシュの若い樹が使われているとのことで、昔から飲んでみたいワインの1つでしたが、飲めないうちにすっかり高くなってしまいました(>_<)
chambertin89
エチケットが好みでないので見送っていましたが、そのような質感なのですね〜φ(•ᴗ•๑) メモメモ ルイジャドなど大手は、いつでもどこでも見かけて買えるので、味わいもありふれた感じを想像してしまいますがw、飲んでみるて驚くことが多い印象です♪
asanomo.
chambertinさん ありがとうございます^ ^ 予想をはるかに超えて来てビックリしました! クロ・デ・ムーシュは高いですが、こちらならフルボトルでも8000円以下で、対してクオリティに関しては並の生産者なら1級畑ともガチで張り合えると思うので、かなりお買い得なのではないかと思いました。 今度はフルボトルで買ってみたいですし、それで美味しかったら、大人買いしちゃうかも知れません(笑)
Johannes Brahms Ⅱ
asanomoさん ホントですよね!そのお気持ちめちゃくちゃ分かります! 特にネゴスもののエチケットは、無機質なフォントくらいしかデザイン要素なくて、「オリヴィエ・ルフレーヴ」と並んで、買う気の起きないワイン達でした。 ところが先日、そのオリヴィエ・ルフレーヴで予想を遥かに超える美味しさを経験してしまい、ドルーアンも偏見無しに飲んでみたいと強く思うようになりました^ ^ 身近過ぎて気付けなかったけれど、実は本当に大切なものは、すぐそばにあった的な?!(笑)
Johannes Brahms Ⅱ
JB様 昔話は嫌われると思いますが、クロ・デ・ムーシュの方がその8000円以下だった頃を知っているので、今のムーシュもこのワインもなかなか買う気になりません(笑) とりあえず、ブクマだけしました(笑)
chambertin89
chambertinさん 本当に良い時代ですよね! その頃と比べてしまうと、今がバカバカしくて何も買えなくなってしまいそうで、それはそれでツラいですね(><) 知らぬが仏の一面もあるでしょうか… 相対的に比べたらこの値段でこのクオリティはなかなかだと思うので、もし機会があれば^ ^
Johannes Brahms Ⅱ
ドルーアンのワイン、大手メゾンとは言え自社畑もありますし、なかなか美味しいですよね。果実がしっかりしていて香り高いところはクロ・デ・ムーシュと近い感じではないでしょうか。
hintmint3
hintmintさん ありがとうございます^ ^ ドルーアン初めてでしたが、香りの立ち上がりが凄かったです。果実が強かったのは若いからかなと思いましたが、もともとそういう造りなのですね! 今改めて思うと、大手メゾンというのもあり、分かりやすく美味しい造りにしているというのもありそうですね。 クロデムーシュやネゴスものも一度試してみたいと思いました!
Johannes Brahms Ⅱ






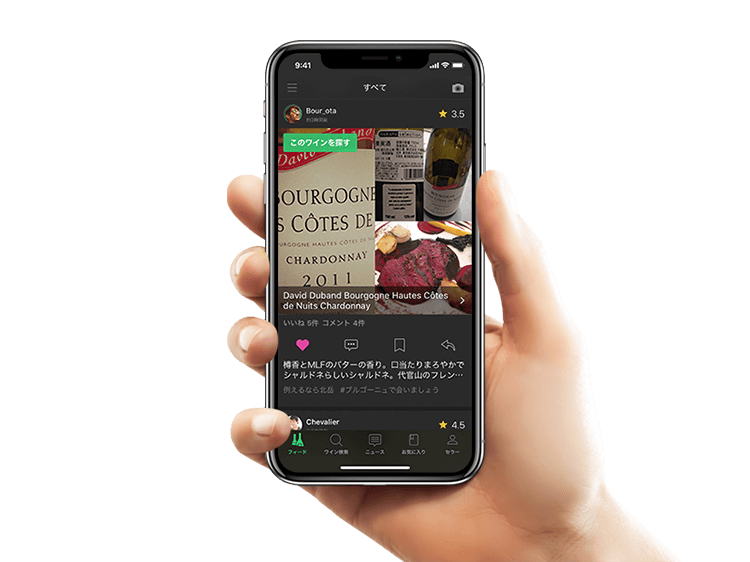
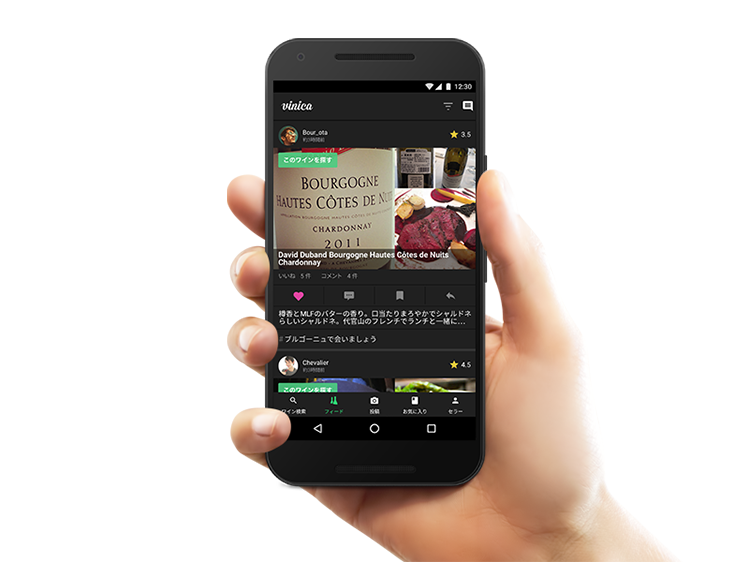


大手メゾンで、いつでもどこでも買えるので、なかなか購入モチベーションが生まれずらかったジョセフ・ドルーアン。 最近無性に気になっていたのですが、行きつけの酒屋さんにハーフボトルが売っていたので試しに買ってみました。 気軽に平日の晩ご飯の時に開けてみたところ、予想をはるかに超える一流の香りが爆発的に広がりおののきました(笑) ルフレーヴの一級畑か何かですか?! はたまたどこぞのグランクリュですか?! というのは流石におおげさかも知れませんが、これまで経験したブルゴーニュのシャルドネにおいて、このクラスの香りが立ち上がるのは超一流の生産者の上級畑であることがほとんどだと記憶しています! 味わいはまだ2018と若いこともありこのクラスの香りを放つ液体なので、まだまだ強い酒質ではありますが、今飲んでも十分美味しいです! 裏書きを読むと、自社畑は全てビオロジックという記載があり、ドメーヌもののようです。その後ちゃんと調べたら、ドルーアンのフラッグシップ「クロ・デ・ムーシュ」の若い樹の葡萄が使われているとのことで、この味わいにも納得です^ ^ ルイ・ジャドもそうでしたが、大手メゾンのワインは、やはりしっかり造られていて美味しいですね。外したくない時には頼りになる存在だと再認識しました。
Johannes Brahms Ⅱ